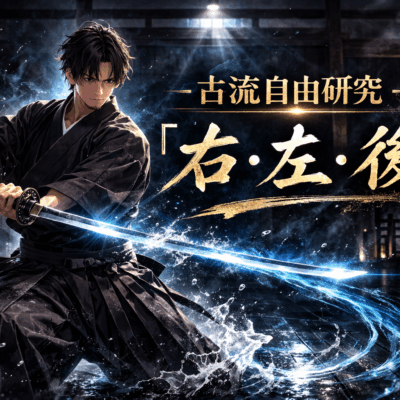皆さん、こんにちは。英(はなぶさ)です。
連日の猛暑、さすがに身も心もぐったりしてきますね。
そこで気分転換も兼ねて、子どもをつれて、滋賀県の琵琶湖へ足を運び、「海水浴」ならぬ「湖水浴」を楽しんできました。

湖面に浮かぶ鳥居と、夏の静寂

湖面に静かに浮かぶ鳥居──白鬚神社の象徴的な風景です。
波音もささやきのようで、酷暑のなかでも心が落ち着きます。
この白鬚神社は、垂仁天皇の御代に創建された近江最古の大社で、
「近江の厳島」とも呼ばれる格式ある神社。
御祭神は、導きの神として知られる 猿田彦命(さるたひこのみこと) です。
砂浜と、平安の記憶
境内を歩いていると、一基の歌碑が目に留まりました。
そこには、あの『源氏物語』の作者・紫式部が若き日に詠んだ一首が刻まれていました。
-1024x768.jpg)
「三尾の海に 網引く民の てまもなく 立居につけて 都恋しも」
長徳2年(996年)、父・藤原為時の赴任に伴って越前へ向かう船旅の途中、
この地・三尾崎の浜辺で見た漁の風景に、都での日々を重ね、恋しさを詠んだと伝わります。
この地に立てば、遠く平安の世にも思いを馳せることができます。
琵琶湖は近畿の水がめとも呼ばれています。今年は水不足で琵琶湖の水も心なしか少ないように思われました(汗
本日の稽古報告(基本組)
さて、本題に戻りまして──
本日の稽古は「基本組」を中心に、足運び・構え・抜刀納刀を丁寧に確認しました。
暑い中ではありましたが、集中力を切らさず稽古に取り組む姿が印象的でした。
今回は山本さんと宇陀さんの組稽古の様子もご紹介します。
お二人からも鋭い質問がありましたので、皆さんの参考になればと思い、ここに共有します。
Q.「片手切りをすると、どうして斜めに流れてしまうんでしょうか?」
A:英の回答
実は―― 片手切りが斜めに流れるのは、ある意味「正しい動き」 でもあるんです。
というのも、私たちは刀を左腰に帯びているため、片手で抜きつけた際、切先は自然と左から右へ斜めに流れていく動きになります。
これは刀の構造と体の動きからくる、いわば必然の軌道です。
逆に、右から左へ斜めに袈裟に切る動作は、諸手(両手)で行うことが基本です。
ですので、「まっすぐ切れない」と悩む必要はありません。むしろ、斜めに抜ける軌道を理解し、その動きの中で刃筋を安定させることが大切になります。
動きの意図を理解すると、稽古の視点がひとつ増えるかもしれませんね。
Q:「納刀がうまくできません……どうすれば?」
A:英の回答
納刀がうまくいかない――これは多くの方がぶつかる壁ですね。
ですが、コツをひとつ覚えるだけで、驚くほどスムーズになることもあります。
そのコツとは、「刀に鞘を合わせる」という逆転の発想です。
納刀では、つい「刀を鞘に納めよう」としてしまいがちですが、実は刀の位置は動かさず、鞘の方を合わせていくのが理にかなっています。
つまり、主役は右手ではなく、鞘を持つ左手。
刀を構えた位置からブレさせず、左手で鞘をコントロールして、自然に鞘口を刃筋へと誘導していく感覚を掴んでみてください。
納刀のときは、ぜひ左手の動きに意識を集中させてみましょう。
鏡を見ながらゆっくり動きを確認するのも、効果的な稽古になります。
初心者のうちは様々な疑問が出てくるものです。逆に高段になると、疑問すら浮かばなくなり、漠然と何も考えない稽古になってしまいます。こんな質問をしてもいいのかな?と思うかもしれませんが、今のうちに色々質問してください。
次回も、基本を大切にしながら、ひとつひとつ丁寧に積み上げていきましょう。
暑さに負けず、静かに燃える夏の稽古を。
では、また!