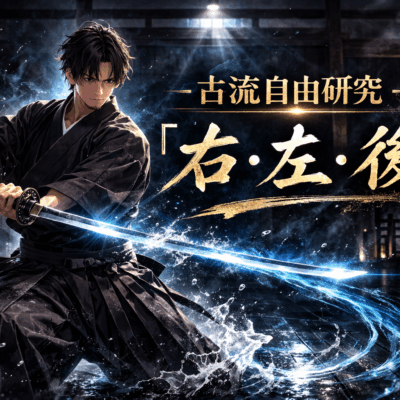こんにちは。居合道ブログ管理人の英(はなぶさ)です。
梅雨の合間に晴れ間がのぞく季節、皆さまいかがお過ごしでしょうか。道場では汗ばむような日も増えてきましたが、外を見ると子どもたちが汗を流しなら遊んでいるのを見ると、ふと心が和みます。
さて、最近、アメリカがイランの核開発施設に対して「バンカーバスター(地中貫通爆弾)」を投下したという報道がありました。
表向きには抑止のための攻撃だとしても、実際にそこで働く人々、暮らしている人たちへの配慮がどれほどあったのでしょうか。テレビの画面の向こうで映る出来事が映画の中の世界でなく、現実の世界の出来事であることが恐ろしくてなりません。
世界の構図が、力を持つ国が持たない国を封じ込める「弱い者いじめ」のように映ることがあります。
そして、その渦中にあって日本がこれからどのような立場を取っていくのか。
平和国家としての矜持を保ち続けられるのか。これは私たち一人ひとりに問われていることなのかもしれません。
■教会で聴いたオルガン、平和の福音
話は変わりますが、先日、大阪の教会で行われたオルガンコンサートに足を運びました。
場所は歴史ある礼拝堂で、荘厳な空間に響くパイプオルガンの音が、静かに心に染み入りました。

(写真①)築100年以上の教会

(写真②)前方の礼拝壇に向かって整然と並ぶ椅子。やわらかい光とともに、祈りの場が整えられている

(写真③)二階にあるのがパイプオルガン、通常のオルガンと違って建物全体に響く音色がしました
このような空間で音楽を聴くと、音とは単なる娯楽ではなく、世界共通のものである気がします。主催者の話では音楽を通じて平和の大切さを訴えているとのことで深く共感しました。
刀の「斬る」という所作が、内なる自分を律するためのものならば、
音楽は他者との心の距離を縮めるための「架け橋」となるものだと思います。
■番外(心を整えるひととき)
オルガンコンサートの前に立ち寄ったのが、教会の裏にあるカフェ「イルベッカフィーコ
(IL BECCAFICO)」。
静かで落ち着いた雰囲気の中、ガラス越しに柔らかな陽が差し込み、時間がゆっくりと流れているような空間でした。
ふと隣の席に目をやると、年配のご夫婦が赤ワインを片手に静かに語らっていました。
ご主人が、カフェの歴史について奥様に話している様子がとても品があり、長年連れ添ってきた夫婦の「粋」というものを感じました。
言葉を選びすぎず、でも丁寧に、互いを思いやるような会話――まさに理想の関係だと感じさせてくれるお二人でした。
そして、出てきた前菜がこちら。

■願いはただ一つ
居合道も、音楽も、そして日々の食事も――
本来はすべて、「命を守る」ために生まれた文化です。
刀を抜くことは、自分を律し、他を守るため。
音楽は、心を癒し、人と人とをつなぐため。
そして食事は、心と体を養い、誰かと穏やかに過ごすためにあるものです。
だからこそ、これらが日常の中にあることの意味を、私たちはもっと大切にしたいと思うのです。
争いや支配ではなく、調和と尊重を育む社会であるように。
オルガンの音が静かに教会に満ちていくように。
刀がすっと鞘に収まるように。
世界が、静かに、確かに、平和へと向かっていきますように。
争いが絶えない世界でも、こんな静かな時間がある。
だからこそ、守りたいんです。私たちの“日常”を。
―― 居合道ブログ管理人・英(はなぶさ)