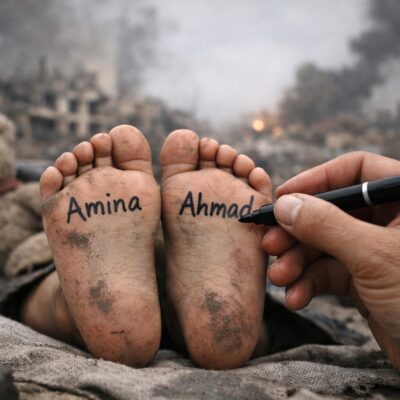【特別講師講習会レポート】2025年4月5日・6日 テーマ「気づき」
春の陽気が感じられる中、4月5日・6日に開催された派遣講師特別講習会に参加しました。今回の講習テーマは「気づき」。技の細部を見直し、居合の奥深さに改めて向き合う時間となりました。
開会式より
開会式では、「成長のためには“気づき”が必要。その“気づき”は日々の“稽古”から生まれる」とのご挨拶がありました。稽古とはただ動作を繰り返すのではなく、そこから何を感じ、何を学び取るかが重要であると改めて感じさせられました。
各本目のポイントと気づき
一本目「前」
振りかぶった際に剣先が下がらないよう意識。特に振りかぶりの手の内と切り下ろした後の手の内の違いを理解することが大切です。
また、鞘引きの動作が剣筋に大きく関わるとの指摘がありました。
三本目「受け流し」
受け流す際には、刃を斜めに保ちつつ、相手の攻撃を逸らして切り返す。ここでは「ただ動く」のではなく、相手の動きに応じた理合いが求められます。
四本目「柄当て」
六本目の「諸手突き」も同様ですが。“刺さっている”感覚を持つことが重要とのこと。納刀では人格が表れるとも言われており、細部まで丁寧な所作を心がけたいところです。
五本目「袈裟切り」
相手の胴が開いた瞬間を逃さず、意識的に“機”を捉えて切ることが求められました。
六本目~十二本目
特に印象深かったのは六本目の「突きの動き」。実際に突きの動きを体感し、自然な動きを意識することが大切と指導を受けました。
また、十一本目・十二本目では「前に立ってもらう」ことで相手を強く意識し、技の理合いの違いを体感することができました。
実技以外の学び ―稽古に挑む心構え
講義では、「自分の技を自分で磨く意識」が強く説かれました。
特に印象的だった言葉がこちら:
- やっている居合とやる居合は違う
- 「もっとこうしてやろう」と思う心が気づきにつながる
- 無理のない居合、無駄のない居合を目指す
さらに、「教本を読む」のではなく、「教本を理解し、自分の言葉で解釈する」ことの大切さが語られました。
イメージする稽古の重要性
居合は仮想の敵に対して行う武道ですが、空手の清水選手が実像を意識して稽古しているように、居合においても「実像として仮想敵をイメージする」ことが効果的であると学びました。これにより、動作に説得力が生まれ、技の精度も上がります。
おわりに ― 継続は気づきに通ず
今回の講習を通して、細かな動作一つ一つにどれだけ意識を向けられるかが、自身の成長につながることを実感しました。
「わかった気になる」のではなく、「わかろうとする姿勢」を持ち続けること。
それこそが、真の「気づき」につながる第一歩なのだと思います。
これからの稽古でも、学んだことを一つずつ意識しながら、“やる居合”を目指して精進していきたいと思います。
特別講師紹介
今回の講習会において、深いご指導と数多くの「気づき」を与えてくださった特別講師をご紹介いたします。
草間 純市(くさま じゅんいち)先生
居合道範士八段・剣道教士七段。
昭和24年(1949年)、新潟県三条市にて、初代館長・草間昭盛氏の長男として生まれる。小学校5年生の頃より、父昭盛氏のもとで剣道・居合道の手ほどきを受け、以後たゆまぬ修練を積む。現在は全日本剣道連盟 居合道委員会 委員長(2019年6月より)として、全国各地での講習・審査を通じて後進の指導に尽力されている。
そのご指導は、技の理合いと所作の美しさにとどまらず、「心のあり方」にまで及ぶ深みを持ち、多くの修行者に感銘を与えている。
草間先生の一言ひとことに、目からウロコが落ちる思いでした。 まだまだ“気づけていない”ことが、自分にはたくさんあるんだと実感……。 もっともっと稽古を重ねて、技と心を磨いていきたいと思います!